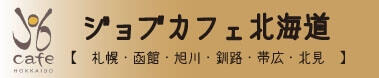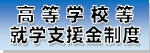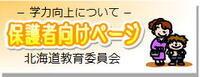Q-3 ①探究のテーマを決まる際に、SDGsなどの大枠を設定する方が、生徒は取り組みやすいと思うようですが、どうですか。 ②生徒が確実にテーマの設定や課題の設定ができる方法はありませんか。
A-3
A-3-1
テーマ設定ですが、Q-2の「表面張力について」のような大きなテーマではなく、問いである「コップの水に一円玉は縦に積み上げて何枚浮かぶのか」といった具体的なテーマを考えさせることが大切です。Q-2でも書いたように、筆者は問いの提示が探究の過程で最も難しいと考えています。質問の趣旨も曖昧なテーマをどう具体的な問いにするのかということだと考えました。
確かに「SDGs」といった大枠を提示して、生徒にテーマを考えさせる方が、具体的なテーマ設定に向けて取り組みやすく、本校普通科でもそのように指導しています。大枠を提示することでテーマを設定するための下調べの時間を短くするメリットもあり、その効果は大きいと思います。本校普通科1年生の探究活動では、「大枠のテーマを選び、そのテーマについて調査等を行い、その中から自分に興味関心のある具体的なテーマへと成熟させる」という経験をさせています。
しかし、探究活動をはじめたばかりの学校では、大枠を提示してもなかなか決まらないのではないかと感じています。その理由ですが、多くの生徒は先輩方が取り組んだ具体的なテーマ(例えば「食品ロス削減が飢餓を救う-世界の課題、ひとりの責任-」「差別や不平等をなくす-誰もが幸せな社会に-」「識字率を上げるには」「水と世界とトイレ」など)を見て、こんなテーマで良いのか、とテーマのイメージを膨らませ、テーマを設定し、そのテーマから問いを立てているからです。
まとめると、大枠を設定するメリットは「下調べの時間を短くする効果がある」「先輩方のテーマを参考にしやすくなる」ことだと思います。この2つのことは、テーマを絞り込む効果があり、結果としてテーマを設定しやすくなるのではないでしょうか。
A-3-2
テーマを設定する練習を工夫することも必要です。例えば、「シーズ志向的問い」という考え方があります1)。シーズ試行的問いとは、与えられた条件の中で問いを立てる練習をする方法です。具体的には、「新聞紙の活用方法を考えよう」「光度計を使ってできる研究を考えよう」「物理教室の○○、□□、自分で考えた装置1つまで、でできる研究を考えよう」といった課題を与えます。シーズ志向的問いは、練習としてではなく、探究活動そのものの課題として、1年かけて探究させてもかまいません。複数のシーズの中から課題を選ぶようにすると、学年単位での探究活動でも問いを立てやすくなるのはないでしょうか。
また、学年全体で、「表面張力」ような曖昧なテーマを共通の課題として提示し、マインドマップやKJ法などを利用して、具体的な「問いの提示」をまでを経験させる、という練習はどうでしょうか。1時間または2時間の授業です。グループワークで一つのマインドマップを書かせ、問いを立てさせ、その問いをクラス全体でシェアするということも可能です。シェアすることで、問いや問いを出す過程の多様性を生徒が経験すると、自分が問いを立てるときの参考になるでしょう。
1)高校生の研究におけるシーズ志向的問いの見つけ方,関根 康介,物理教育2023年71巻4 号p. 288-292