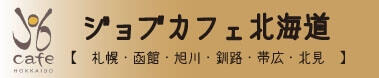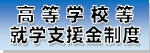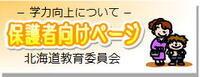Q-4 ①Youtube等の実験を確かめたいという内容が多く困っています。どうしたら良いですか? ②1年で結果が得られないような壮大なテーマを設定する生徒にどのように声をかければ良いですか。
A-4
Q-2やQ-3とも関わりますが、まずは(Youtube上で公開されている実験は、危険な場合もあるので、安全面を教員が確認した上で)取り組ませてみてはどうでしょうか。探究や課題研究のきっかけは多種多様で、意外と些細なことも多いものです。問題は、探究のテーマ(問いと言っても良いかもしれません)を如何に発展させていくかだと考えます。筆者は「テーマは成熟する」「テーマを成熟させる」と表現しています。また、ほとんどの研究は先行研究を再現するところから始まります。Youtube等の実験も先行研究ととらえてみてはどうでしょうか。
筆者が指導した理科部の活動で生徒が「水に洗剤を入れて船が進む動画をYoutubeで見て面白かったのでやってみたい」と提案してきました。筆者は「とりあえずYoutubeの実験を再現して、キーワードを探してごらん」と指導したところ、しばらくして生徒から「表面張力」と回答がありました。そこで筆者は「表面張力を測定してごらん」という課題を出しました。その課題に取り組む過程で、「洗剤の濃度と船の推進力の関係」という課題を設定し、論文を仕上げていきました。
本校の課題研究でも「水の上を(タイヤで)走っているYoutubeの動画を試したい」とう当初のきっかけから始まり、「チョロQを水の上で滑走させるための条件」という課題を設定し、チョロQを四輪駆動や六輪駆動に改造したり、スキー板状の補助具を開発したりして実験を続け、「チョロQが水の上を滑走するときの水による抵抗力は速さに比例する」とい結論に至る研究をしたグループがあります。
紹介した2つの事例は、Youtubeで紹介されている実験の再現等をきっかけに、新たな疑問を見つけ、その疑問を解決するための方法を模索するという探究の過程に入っていくところが共通しています。先ほども書いたように「テーマが成熟」した例です。そのときの教員の役割は、単に再現するだけでなく、再現する過程で新たな疑問を見つけるよう促すことだと考えます。声のかけ方はQ-1を参照してください。
「壮大なテーマ」を設定する生徒もよくいます。この場合も、まずは考えさせてみてはどうでしょうか(実験できない場合が多いので、「再現する」ではなく「考える」「調べる」です)。例えば「宇宙」や「ブラックホール」というテーマを設定したとします。筆者は、はじめに「壮大すぎてできないのは分かるよね、でも面白いかもしれない。そこから実現可能なテーマに成熟させてみよう。」と声をかけています。そして「宇宙から連想できるワードをマインドマップを使って広げてみよう」「マインドマップに出てきたワードをネットで調べてみたら」と指導しています。マインドマップは多様な広がりを見せますが、例えば「宇宙」→「銀河」→「天の川」→「七夕」と広がっていき、最終的に「啓成高校生は七夕を知っているか?」という調査をともなった研究になっていくかもしれません。
経費的制限や研究倫理の問題、実現可能性等の問題のため、せっかく生徒がテーマを考えても、実際には高校生が取り組むことができない場合も多々あります。生徒の発想を「実現不可能」等の理由であきらめさせるのではなく、当初のテーマを尊重したうえで、生徒には「お金がかかる」「動物実験は倫理上できない」「実験できない」等の理由を説明し、そのテーマをどう成熟させるかを考えさせてはどうでしょうか。