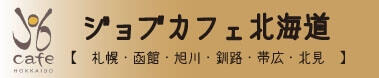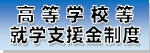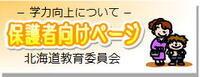Q-2 ①調べ学習や確認実験で終わってしまい、探究活動になりませんがどうしたらよいでしょうか。 ②生徒のレベルにあわせてどこまで求めるのか難しいと感じています。どのようにゴールを設定したら良いですか。
A-2
この二つのご質問は「ゴール設定をどうするのか」ということだと感じました。特に普通科での探究活動で問題になると思います。
筆者は本校普通科の探究活動(FV)を担当する先生方に次のようにお願いしています。「調べ学習や確認実験でもかまいません。ただし、調べた結果や確認実験の結果から、各自が疑問に思ったことや不思議に感じたことを見つける(問いの提示)よう指導してください。ここまででも十分ですが、さらに、疑問に思ったことをどう解決するのかを考えられれば(解決方法の試案の提示)さらに良いです。」
なぜこのように指導するかというと、実は探究の過程で「問いの提示」が一番難しいからです。生徒は、いきなり問いを立てようとする場合が多いのですが、問いを立てるためには、その問いの背景にある膨大な量の下調べが必要です。
例えば、生徒が「表面張力」について調べたいと考えたとしましょう。「表面張力について」では問いを立てたことになりません。そこで「表面張力」についてネットなどで調べることになります。調べる中で「コップの水の表面張力」に注目したとします。そうすると表面張力により水面が盛り上がることや洗剤を入れると表面張力が弱くなること、などいろいろなことが分かります。そこで改めて問いを考えさせると、やっと「コップの水に一円玉は縦に積み上げて何枚浮かぶのか」いう問いにたどりつきます。
もう一つ例を挙げましょう。「地域おこし」に興味を持った生徒がいたとします。ネット等で「地域おこし」を調べたところ、「お祭り」や「商店街」、「イベント」などのキーワードが出てきました。そこで自分が住んでいる街を調べたところ町内会で盆踊りをしていることが分かりました。その生徒は「地域おこし=観光振興」というイメージがあったので不思議に思い、町内会の役員に聞き取りをしたところ「住民のつながりをつくりたい」という回答があったので「高校生は街作りに貢献できるのか」という問いにたどりつきます。
筆者の経験では、調べたり確認実験をするのにも時間がかかりますが、そこから具体的な問いを立てるのにもハードルがあり、(授業時間のみの指導であれば)問いにたどり着くのに10時間程度(2ヶ月~3ヶ月)かかります。はじめの問いを立てることができれば、「洗剤を入れるとどうなるか」など,探究の過程を経て問いを成熟させることもできるようになります。7月から指導をはじめたとして、夏休みを挟みやっと11月になって問いにたどりついた時には、1月の発表会に向けた準備をはじめないと間に合わない状況です。
無理をすると生徒主体にならないというのが「問いの提示」を目標とする一つの理由です。もう一つの理由は、高校の探究活動では「探究の過程を生徒に体験させる」ことが大切ですが、探究の過程で最も重要な「問いの提示」を重視したということになります。
「生徒のレベルに合わせて」ということですが、ほとんどの生徒は、探究の過程を経験したことはありません。超がつくような進学校の生徒も進路多様校の生徒も、条件は同じだと考えています。生徒の実態に合わせて、問いの立て方も多様にはありますが、「問いの提示」を一つのゴールにすると良いのではないでしょうか。
ところで、筆者の経験では、「問いの提示」から探究の過程を「新たな問いの提示」まで進むグループが、学年の中に1割程度現れます。「2年生の発表を1年生が見学する」ことや「優秀な発表を学年全体でシェアする」などの活動を何度か続けると、良い探究活動のイメージが後輩達に引き継がれていき、探究活動のレベルが上がっていくと感じていて、後輩たちに対して5年後の探究活動の種をまいていると考えています。