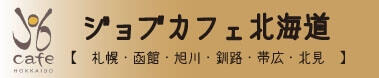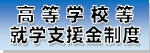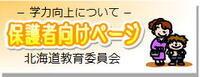Q-1 ①生徒の探究活動に伴走すると言われるがイメージがわきません。どんな生徒に、どのように指導するのが良いですか?生徒をただ見ているだけになってしまうのですが・・・。 ②教員が全く知らない内容の研究テーマについて、指導することはできますか。
A-1
少人数(1人~5人程度)に担当教員を1名つける場合と、10人~40人の生徒を1名の教員で指導する場合とで対応が違います。
A-1-1
前者の場合は、伴走というより共同研究者というスタンスが大切だと考えています。この場合は、指導者と生徒が密接に関わりながら探究活動を進めているはずです。筆者の場合は、一般的な実験の方法論、グラフの作り方、データ処理の方法、発表の仕方など、技術的なことは、当然生徒は知らないので、かなり詳細に指導します。また、内容については、自分も楽しみながら指導していて「○○を知りたいんだけどな」「○○が分かればもっと面白そうだよね」「僕はアイデアがあるんだけど、君たち考えてみたら」などの言葉をかけます。もちろん全てを指示するわけではなく、アイデアを出しても実験方法は工夫させたり、アイデアのうち一部だけ伝えたりといった、生徒の主体性を引き出す工夫をしています。
共同研究者なので、全く知らない内容のテーマでも、「自分も分かりたい」ということを生徒に伝え、一緒に研究すると良いのではないでしょうか。その方が、生徒のモチベーションも上がると思います。
A-1-2
後者については伴走という言葉がぴったりだと思います。詳しく説明しましょう。担当者は、「時間や進捗状況の把握」「内容の指導」が主な仕事になります。
「時間や進捗状況の管理」は文字通り「今日は○○まで進めよう」「あと○回でここまでならない?」「○○までできているのでこのあと○○をしよう」「もう少し進めないと間に合わないよ」など、生徒に今後の目処を与えることです。また、学年の担当者との連絡調整や外部機関との連携が必要なときの指導も含まれます。外部機関との連携を模索する場合、学校によっては生徒が教員を通さず直接連絡する場合もあるようですが、一般的には担当教員の許可を得たうえで、初回は担当教員から外部機関に依頼する場合が多いと思います。
質問は「内容の指導」が念頭にあると思います。先生がアイデアを出したり、調べる内容や考察まで口を出すのは、もちろん良くありません。しかし、何も指導しないのも良くありません。生徒は「何を調べるべきか」や「どのように探究するのか」等を知っているわけではないからです。筆者は担当の先生方に「進捗状況を確認するときに一言コメントを言ってください。難しく考える必要はありません。内容について直接指導するのではなく、『面白いね』『ここが分かりにくいね』『もう少し突っ込んで考えてみたら』『最近ネットで似たような記事があったよ』『ここで仮説を立ててみよう』など、おおざっぱなコメントでかまいません。」とお願いしています。つまり、「調べが足りない」と判断したときは、「○○を調べてみよう」と指導するのではなく「○○が分かりにくいので、もう少し調べてて、考えてみたら」と生徒の活動を促します。その繰り返しが伴走につながると考えています。
このように考えると、全く知らない内容の研究テーマでも指導できるのではないでしょうか。