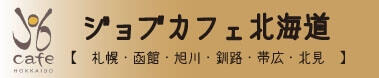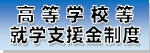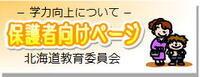Q-5 ①生徒が主体的に探究に関わっていません。効果的な指導方法はありますか。 ②進学校で、「受験に関係ないから」と意欲のない生徒にはどのようにアプローチすれば良いでしょうか。
A-5
主体的に探究に関わらない生徒は、学校の活動や一般の授業にも主体的に関わっていないのではないでしょうか。この問いも古くて新しい問題で、特効薬は無いと思います。
皆さんは、「授業に主体的に関わらない生徒」、つまりやる気の無い生徒にどのようにアプローチしますか。「怒る」や「課題を強制する」等のアプローチでは、一時的な効果はあるかもしれませんが、永続しないことは経験的にご理解いただけると思います。その生徒は、授業が理解できないから取り組まないのかもしれませんし、何をすれば良いのかが分からず右往左往しているのかもしれません。また、私生活や人間関係で悩んでいて授業どころではないという理由かもしれません。前者の「授業が理解できない」等の理由であれば、わかりやすい授業を心がけ、一人ひとりが何をすべきかをはっきりさせ、「面白い」「ためになる」と思わせる授業となるように工夫すると思います。
筆者は探究活動も同じだと思います。筆者の場合は、1年生前半の探究活動導入部で、チームビルディングもかねて、マシュマロチャレンジやNASAゲームなどのゲーム的要素のある楽しめるプログラムを入れています。また、やはり1年生前半の探究導入部で、Q-3にある「シーズ思考」の探究活動のように比較的取り組みやすい課題を設定することも効果的だと考えています。また、「○○を解決するための方法を考えよう」など、探究の過程の一部を体験させるような課題も取り組みやすく、達成感も得やすいのではないでしょうか。導入の段階で「探究活動は楽しい」と生徒に感じてもらえることが大切と考えています。
はじめにも述べたように、主体的に取り組まない理由は生徒一人ひとり違い、特効薬はないのは、一般の授業と同じです。ベテランの先生の授業を見学し、すごいと思ったことはありませんか。私たちが経験を積む中で、そのノウハウを積み上げていくことが、問題解決の近道なのかもしれません。
「受験に関係ないから」主体的に取り組まない生徒への対応も、やはり1年生前半の探究導入部で行うのが効果的です(2年生になってからでは手遅れかもしれません)。何のために探究活動をするのかを理解してもらえば、探究活動が、実は受験にも役立つことが理解できるはずです。
第一に、探究活動は「課題を設定し、解決する」方法を身につけることです。このことを受験に当てはめてみましょう。受験では、「今自分に何が足りないのか、何を勉強すべきなのか」という課題を見つけ、「どのように勉強すれば効果的か」という解決策を設定し、「勉強」して、「その結果を分析」し、「次に何を勉強すべきか」を考えますね。まさしく、探究の過程です。つまり、探究の過程を身につけることは、受験勉強を自分自身で組み立てられるようになる力を身につけることであり、受験生に最も必要な力です。
探究活動が受験に役立つテクニカルな理由もあります。国語や英語、地歴・公民の入試問題で顕著ですが、一見関係ないAとBの事象を組み合わせることで、答えが導かれることがあります。理科のような理系の教科でも同様です。一見結びつかない事象を関連付けることができる力は、探究活動のような、総合的な学びの過程で身につけられるものです。
ここで示したように探究活動は受験の基礎的な土台を作るために重要な学習だということを、1年生前半の探究導入部で生徒に理解してもらうことが大切ではないでしょうか。