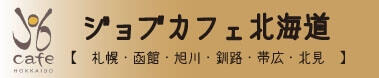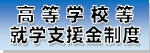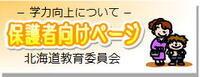6月12日(木)の5校時に、第3学年を対象とした進路講演会を実施しました。 今回は、札幌千秋庵株式会社 代表取締役社長 中西克彦 氏を講師にお迎えし、「キャリアドリフトによるキャリア形成〜商社パーソンから老舗菓子企業の社長になるまで〜」という演題でご講演いただきました。 講演では、ご自身のこれまでのキャリアや経験を具体的にお話しいただき、生徒一人ひとりが自分の「やりたいこと」をしっかりと持ち、それに向かって進むことの大切さを伝えてくださいました。「進路は一つではなく、柔軟に変化していくもの」というメッセージは、生徒たちにとって将来を考える上で大きな励みとなりました。 中西様、貴重なお話をありがとうございました。
6月10日(火)17: 00から本校3階大ホールにて今年度の海外研修説明会が実施され、生徒・保護者合わせて66名が参加しました。
はじめに、本校の国際交流の紹介と昨年度参加した外部の国際交流についての情報提供、ホストファミリーの募集についての説明を行いました。
その後、株式会社ISAの平田様より、 イングリッシュキャンプとカナダ研修について、世の中の変化や他国での取り組みを実際に経験することの大切さを含めてお話しいただきました。
また、本校および外部の国際交流に参加した在校生3名が、自身が経験したこと、実際に参加したことで自信がついたことや進路が決まったこと、なぜ海外研修に参加しようと考えたのかなど、パワーポイントを用いて発表し、その中で3名とも共通して、『 迷っているのであれば挑戦するべき!』と話してくれました。
今回の説明会を通して海外研修に積極的に参加し、自分自身に自信が持てたり、新しい目標を見つけたりできる生徒が増えることを願っています。
5月26日(月)5,6時間目
1年生普通科を対象に、FV特別講演を行いました。
探究を深める「対話型論証」と題して、
北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部の田中先生より講義をしていただきました。
これから啓成高校の総合的な探究の時間「Future Vision」が始まります。
自分たちの探究のために、問いを考えるコツを教えていただきました。
生徒達も、問いをあらゆる角度からアプローチし、周囲と共有する体験をしました。
日常のふとした疑問などを掘り下げて、自分自身そして周りの人と対話しながら問いと考えを深めていくことは、今後のFVに必要です。今日の講義は、そのエッセンスを得られた時間となりました。