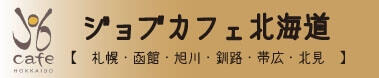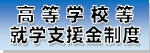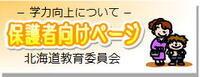2018(平成30)年度 - 活動レポート
北海道大学研修
2019/01/08~01/09 北海道大学研修
日時 1月8日(全日):工学部・理学部(化学)・電子研
1月9日(全日):理学部(数学・生物)
場所 北海道大学理学部・工学部・電子研究所の計6研究室
対象 第2学年理数科 40名
担当 SSH推進部
内容 本研修は9月7日に実施予定でしたが、前日に発生した北海道胆振東部地震の影響で日程を変更して、本日の実施となりました。北海道大学の各研究室では、1日、実験・実習を行いながら最先端の研究に触れてきました。データ取得への厳しい姿勢及び科学的な研究手法・思考を学びました。北海道大学の先生方、貴重な研修機会を与えて頂きありがとうございました。
研修テーマ等:
・数学「3D パズル組上げに挑戦」理学研究院数学部門教授 松本圭司氏
・化学「分子の網で液体を捕まえる~高吸水性樹脂について~」大学院理学研究院化学部門教授 佐田和己氏
・生物「動物の卵子と受精、発生~マウスの解剖~」大学院理学研究院生物科学部門准教授 小谷友也氏
・工学「音を目で見よう~音の波長と周波数の関係から音速を求める~」工学研究院応用理工系学科教授 西口規彦氏
・工学「生物型移動ロボットを動かしてみよう」工学研究院機械知能工学科准教授 原田宏幸氏
・電子研「実験と数学で化学反応や自走粒子運動の秘密を探る」電子科学研究所教授 長山雅晴氏
日本動物学会北海道支部第63回大会
2019/03/23 日本動物学会北海道支部第63回大会
会場 北海道大学理学部
参加者 科学部 1名
内容 科学部の研究グループ(テーマ:対捕食戦略の異なる近縁な陸産貝類二種は、移動速度も異なるのか?)が、高校生による特別発表(口頭発表)部門で、優秀賞を受賞しました。殻を振り回し捕食者と戦いながら逃走するエゾマイマイは、殻を振り回すのに必要な筋力が逃走速度に対しても有効に働いているという仮説を立て、エゾマイマイとヒメマイマイの移動速度を種間比較により検証した成果が評価されました。
第66回日本生態学会神戸大会
2019/03/17 第66回日本生態学会神戸大会
会場 神戸国際会議場
主催者 一般社団法人 日本生態学会
参加者 科学部 1名
内容 科学部の研究(テーマ:ヒメザゼンソウ(Symplocarpus. nipponicus)の開花傾向と越冬戦略)が、高校生ポスター発表会でナチュラルヒストリー賞を受賞しました。啓成高校敷地内自然林に多数展葉するヒメザゼンソウの個体群の継続調査から、密度と開花個体割合、花数と葉枚数・葉サイズとの関係と経年変化、シュートの内部構造等、ヒメザゼンソウの生態を明らかにしたことが評価されました。
HISF ポスター発表会
2019/03/08 HISF ポスター発表会
会場 札幌市青少年科学館
参加者 第2学年理数科 39名
海外研修参加生徒 14名
内容 本校が主催する北海道インターナショナルサイエンスフェアで、課題研究(科学研究)に関するテーマ10件、サスティナビリティに関するテーマ4件の発表を行いました。海外研修参加生徒のグループ(テーマ:Nature of Malaysia)が、Communication 賞で1位を受賞しました。
サイエンス英語特別講座(普通科)
2019/02/05~02/06 サイエンス英語特別講座(普通科)
時間 各クラス2時間
対象 第1学年普通科全クラス
講師 神田外語大学外国語学部英米語学科専任講師 柴原智幸氏
担当 英語教諭、SSH推進部
内容 英語によるポスター発表及び口頭発表に向けて、NHKラジオ英会話講師として有名な、専門的知識を有する柴原先生より科学における英語の使い方等について実践的な指導を受けました。放課後には、2日間にわたり、ボランティアで英語表現の特別講座も開催してくださいました。英語で盛り上がったとても有意義な2日間になりました。ありがとうございます。
サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
2019/02/05 サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
テーマ 「エネルギー保存の法則」
時間 6、7校時
場所 物理教室
対象 第1学年理数科40名
講師 北海道大学留学生12名
オブザーバー 神田外語大学外国語学部英米語学科専任講師 柴原智幸氏
担当 理科教諭、英語教諭
内容 本日は、特別ゲストとして、柴原先生に授業を参観していただき、英語で科学を学ぶ本校の取組について意見を伺いました。授業開始時に、日本語で専門用語を確認する場面があり、常にオールイングリッシュにこだわる必要があるのかどうか担当者として悩んでいましたが、限られた時間で授業を進めるためには、日本語で効率よく説明する場面は必要だとのご意見をいただき、今後の進め方の参考になりました。
環境道民会議
2019/01/23 環境道民会議
会場 札幌国際ビル
主催 環境道民会議北海道
参加者 道民、事業者、行政関係者 約150名
報告者 第2学年普通科2名
内容 道民、事業者、行政が互いの連携のもとで自主的、積極的に環境保全活動取り組み、その活動をより広がりを持ったものとしていくために設置(事務局:北海道環境生活部)された20周年記念「SDGsフォーラム」で、本校の北海道大学と連携したSDGsをテーマとした探究学習(フューチャービジョン)の実践を、本校生徒がパネラーとして報告してきました。参加者からは、生徒の堂々とした質疑応答の姿を評価するコメントをいただきました。
マレーシア熱帯林海外研修
2019/01/05~01/14 マレーシア熱帯林海外研修
参加生徒 第1学年(普通科3名、理数科5名)
同行講師 前サバ大学熱帯生物保全研究所准教授 辻宣行氏
引率 本校教諭 2名
日程
1.05 新千歳空港出発、泉佐野市泊
1.06 関西空港出発、出国
1.07 サバ大学訪問
・プレゼンテーション発表、講義、標本庫見学・実習
クリアスマングローブ森林保護区
・川沿いの動物調査、希少動物保護についての考察
1.08 ポーリン温泉公園訪問
・ 低地熱帯林の植生と林冠観察等
1.09 メシラウ小学校訪問
・ 本校生徒によるサイエンス教室
キナバル国立公園
・ 植物園にて樹木・草本・昆虫等の観察、下部山地林の垂直分布観察等
1.10 サバ大学隣接の海岸及びサバ大学訪問
・ 海洋漂着ゴミ(マイクロプラスチックを含む)調査、講義、環境保全に関する議論
1.11 オールセインツ中等学校訪問
・ プレゼン発表会、科学の授業体験、環境問題議論
1.12 コタキナバル湿地センター訪問
・ マングローブの植林、ガイドウオーク、講義等
1.13-14 コタキナバル空港出発、帰国
研修時の様子
事前研修では、とても消極的だった生徒生徒が、現地で積極的に行動していたり、最終日のオールセインツ中等学校でのプレゼンテーションでは、自分の言葉でしゃべろうとする姿勢が目立ち、生徒の成長が見られた。海洋プラスチック汚染に関するサバ大学、オールセインツ中等学校との協働的な調査は、翌日の新聞記事となり大々的に報じられ、SSH研究指定校の宣伝にもなりました。
道外研修 テーマ : 最先端科学技術
2019/01/09~01/12 道外研修 テーマ : 最先端科学技術
参加生徒 第1学年(普通科3名、理数科12名)
引率 本校教諭 2名
日程
01.09 海洋研究開発機構(JAMSTEC)横須賀本部訪問
・講義、「しんかい6500」等見学、高圧実験水槽圧力実験
01.10 物質・材料研究機構 (NIMS)訪問
・ 超伝導材料、クリープデーターシート、次世代太陽電池、クリーンルーム、超高純度ダイヤモンド結晶、ファイバーフューズに関する講義、実習
01.11 (独)高エネルギー加速器研究機構(KEK)訪問
・ 常設展示見学、筑波実験棟「Bファクトリー実験施設」見学
宇宙航空研究開発機構(JAXA)
・ 運用管制室、宇宙飛行士養成エリア見学
理化学研究所バイオリソース研究センター(BRC)訪問
・ 講義「実験動物の発生工学について」及びラボ見学
01.12 日本科学未来館訪問
・ 館内研修、振り返り
内容
上記の最先端研究施設を視察し、研究者や技術者に直接質問する機会を持つことで、最先端の科学技術に関する理解を深め、研究に対する態度・考え方を学びました。今年度は、もっとじっくり研修先で過ごし、講師と対話しながら学べるように、訪問先を2ヵ所減じて実施しました。研修先から、生徒の積極的な質疑の態度を評価してもらうメールをいただくなど、生徒の意欲にもプラスに働いた研修となりました。
インターネット会議 11月
2018/11/20 U18 インターネット会議 11月
時間 7:50~8:50
場所 物理教室
対象 第2学年普通科 探究「Future Vision」
Sustainable Future Earth選択者22名
担当 理科教諭、英語教諭、ALT
講師 酪農学園大学准教授 吉中厚裕氏
内容 6回目の今回は、本校1グループの発表("Survey on distribution status of Micro plastic")とマレーニー州立高校の2グループの発表("Whales and Plastic Pollution", "Biodegradable Plastics and Marine Wildlife")について質疑応答をしました。プラスチックの話から、ヒゲクジラの繁殖へと話が広がり、なかなか面白い質疑応答になりました。来月は、実際にオーストラリアで、これまでの議論を踏まえて、高校生としてどのようなことができるのかを議論することになります。
サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
2018/11/07 サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
テーマ 「炎色反応」
時間 4校時
場所 物理教室
対象 第1学年理数科40名
参加者 マレーシア高校生5名、JICA研修員11名
担当 理科教諭、英語教諭
内容 トップページ「2018.11.7 JICA研修員訪問」をご覧ください。
水の安定同位体比分析から見た森
2018/11/06 水の安定同位体比分析から見た森
日時 11月6日AM
場所 北海道大学環境科学院
対象 海外研修参加生徒、ホームステイ受入生徒 19名
講師 北海道大学地球環境科学研究院准教授 根岸淳二郎氏
担当 SSH推進部
内容 「さくらサイエンスプラン」により招へいしたマレーシアの大学生・高校生10名と一緒に、水の安定同位体から飲料水の水源地を推定する手法を学びました。高度な内容ですが、現在の高校で学んでいる数学、化学の理解が必要であることが実感できました。研修はすべて英語で行われました。
超小型衛星から見た森
2018/11/06 超小型衛星から見た森
日時 11月6日PM
場所 北海道大学創成研究機構宇宙ミッションセンター
対象 海外研修参加生徒、ホームステイ受入生徒 19名
講師 北海道大学大学院理学研究院教授 高橋幸弘氏
担当 SSH推進部
内容 「さくらサイエンスプランにより招へいしたマレーシアの大学生・高校生10名と一緒に、森林生態系を光学、宇宙技術を活用してモニタリングする手法を学びました。高校では詳しく学ばないスペクトルについて学ぶことができました。研修はすべて英語で行われました。
科学デザイン
2018/10/30 科学デザイン
場所 物理教室
対象 第1学年理数科 40名
担当 理科教諭
内容 「科学デザイン」は、科学研究を行う上で大切な研究のアプローチ(道筋)をデザインする力を身につけてもらうために行っている学習です。通常の学校では学ばない、SSH指定校ならではの学習の1つです。今年度は、科学英語でも、この科学デザインの視点を取り入れた学習を取り入れています。本日は、その1回目として、卒業生が行った課題研究を事例に、「なぜ」と疑問に思ったことを、「どのような仮説を立てて、どのように研究を進めていくと、その解決に繋がるのか」について、グループで議論を行い、研究の進め方について学びました。今後、「課題研究から学ぶ2、3」、「科学史から学ぶ」を予定しています。
U18インターネット会議 10月
2018/10/16 U18インターネット会議 10月
時間 7:50~8:50
場所 物理教室
対象 第2学年普通科 探究「Future Vision」
Sustainable Future Earth選択者23名
担当 理科教諭、英語教諭、ALT
講師 酪農学園大学准教授 吉中厚裕氏
内容 5回目の今回は、本校2グループの発表("How plastic waste effects the ecosystem", "Micro plastic’s absorption of harmful substances")とマレーニー州立高校の3グループの発表("Plastic Production", "Plastic Water Bottles are Effecting Marine Wildlife", "Microbeads")について質疑応答をしました。発表数が多かったため、十分な質疑応答ができなかったのが、残念でした。次回は、質疑応答に時間を取れるように、発表数を減らします。
課題研究サイエンス
2018/10/12 課題研究サイエンス
場所 化学教室他
対象 第2学年理数科40名
内容 4月から進めてきた課題研究も12月の発表会まで残すところ2ヶ月となりました。各班とも、データを取るための装置づくりや実験方法の工夫など、実験データを集める段階となって来ました。本日は、寒地土木研究所の研究員にモデル実験の進め方についてアドバイスをもらいに行っているグループもあります。このように、研究所や大学の研究者にお世話になりながら、研究を進めるようになって来ています。ご協力、ありがとうございます。
啓成SSH in 光の広場
2018/10/08 啓成SSH in 光の広場
場所 サンピアザ光の広場
講師 本校希望者 37名
対象 小学生や一般来場者約1000名
共催 札幌市青少年科学館、北海道博物館
内容 近隣の小中学生を対象に、サイエンス教室等を開催し、科学の楽しさを伝えてきました。講師となった本校生徒は、自分の頭で考えて、来場者の属性の違いに合わせてコミュニケーションをとることを学ぶことができました。参加者からは、大変、好評を得ることができました。
【ステージ・パフォーマンス】
・博士とサイエンス「風船マジック」「ポップコーンをつくろう」
【体験型講座】高校生とサイエンスを楽しもう
・テーマ「科学実験」13ブース
・テーマ「宇宙」青少年科学館との連携
・テーマ「生きものたちの北海道」北海道博物館との連携
サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
2018/09/25 サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
テーマ 「札幌軟石の生い立ちを探る(火山災害)」
時間 6・7校時
場所 大ホール
対象 1学年理数科40名
講師 北海道大学留学生7名、ALT 3名
担当 理科教諭、英語教諭
内容 道内研修Aの事後研修を兼ねて、札幌軟石の形成過程を、留学生TA及びALTと一緒に探究的にオールイングリッシュで学びました。科学的アプローチをデザインする力の育成として、はぎ取り地層から科学的な事実を読み取り、札幌軟石の産状と分布、シラス台地の生い立ちなどの知識を基に、札幌軟石の形成過程を論理的に考察することを学びました。TAからの質問にも頑張って答えようとする姿勢が目立ちました。
U18インターネット会議
2018/09/18 U18インターネット会議
時間 7:50~8:50
場所 物理教室
対象 2学年普通科 探究「Future Vision」
Sustainable Future Earth選択者20名
担当 理科教諭、英語教諭、ALT
講師 酪農学園大学准教授 吉中厚裕氏
内容 4回目の今回は、本校3グループが小樽ドリームビーチ及び室蘭イタンキ浜で行った海岸調査(漂着ゴミとマイクロプラスチック)についての報告とマレーニー州立高校の2グループの生態系への影響についての探究について、質疑応答を行いました。ドリームビーチの調査地点の砂には、マイクロプラスチックはほとんど含まれていませんでしたが、イタンキ浜にはビーズ状のマイクロプラスチック(レジンペレット)が含まれており、海洋汚染を実感として捉えることができました。
サイエンス英語I 道内研修イングリッシュポスター作成
2018/09/11 サイエンス英語I 道内研修イングリッシュポスター作成
場所 コンピュータ室
対象 1学年理数科 40名
講師 北海道大学留学生 7名
ALT 3名
担当 理科教諭
内容 夏休みの道内研修A・Bで学んだ内容を11月に招へいするマレーシア高校生達へ伝えるための英語ポスターの作成に取りかかりました。留学生及びALTから分かりやすく伝えるための英語表現の指導を受けました。来週も来校していただき、ポスターを完成させる予定です。
U18インターネット会議
2018/08/16 U18インターネット会議
時間 7:50~8:50
場所 物理教室
対象 2学年普通科 探究「Future Vision」
Sustainable Future Earth選択者23名、
オーストラリア研修参加他校生 5名
担当 理科教諭、英語教諭、ALT
講師 酪農学園大学准教授 吉中厚裕氏
内容 3回目の今回は、マレーニー州立高校生が現地で行った海岸調査の速報について、質疑応答を行いました。質疑の途中、意味の違う同じ綴り・発音の単語で質疑応答がかみ合わない場面がありましたが、実践的な英語の学びにもなりました。
12月の重点枠SSHオーストラリア海外研修に本校生徒と一緒に参加する東高校と国際情報高校の生徒も事前研修の一環として参加してもらいました。
SSH全国研究発表大会
2018/08/08~08/09 SSH全国研究発表大会
ポスター発表賞受賞
発表テーマ 「白黒こまの多色現象」
会場 神戸国際展示場
参加者 谷優輔(理数科1年) 椿原義史(理数科1年) 今井真理子(理数科1年)
内容 白黒こまを回転させると有彩色が見えるという現象のメカニズムを研究した3名が、平成30年SSH生徒研究発表会で発表を行ってきました。全国のSSH指定校及び過去に指定経験のある学校206校が集まり、審査委員の審査により21校に授与されるポスター発表賞を受賞しました。発表を聞いた人達からは、「興味深い研究である」、「そんな現象があるとは知らなかった」などの声が聞かれました。
U18インターネット会議
2018/07/24 U18インターネット会議
時間 7:50~8:50
場所 物理教室
対象 2学年普通科 探究「Future Vision」
Sustainable Future Earth選択者23名
担当 理科教諭、英語教諭、ALT
講師 酪農学園大学准教授 吉中厚裕氏
内容 2回目の今回は、「海洋プラスチック汚染と生物多様性の保全」を大テーマとする協働プロジェクトに関して、グループごとに行う調査・研究のテーマ及びその計画の概要を互いに報告し、質疑応答を行いました。
本校のテーマ
「Hidden micro plastic (The Japan Sea)!!」、「About the micro plastic pollution in the Pacific Ocean」、「Ocean plastic pollution」、「How marine plastic pollution will affect ecosystems in the future」、「Whether harmful substances are absorbed to microplastic」、「Survey on distribution status of Products that contain microbeads」
マレーニー州立高校のテーマ
「Microbeads are affecting Marine filter feeders」、「Plastics water bottles are effecting marine wildlife」、「Biodegradable Plastic and it's impact to marine life」、「Plastic bags and their effects on sea turtles」、「Microplastics Interfering with our Food Chain」、「Plastic Society」、「Whales and plastics」、「The Affect of Plastic Straws」
サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
2018/07/24 サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
テーマ 「プレートテクトニクス(北海道の形成)」
時間 6・7校時
場所 物理教室
対象 1学年理数科 40名
講師 北海道大学留学生 10名
担当 理科教諭、英語教諭
内容 道内研修Bの事前研修を兼ねて、北海道の中軸部が形成される過程を、探究的に留学生TAと一緒にオールイングリッシュで学びました。科学的アプローチをデザインする力の育成として、北海道の化石・岩石・高山植物、海底地形、太平洋の海底火山の観察事実を統合的に考察することにより、北海道がどのようにして形成されてきたのかという大テーマを解決に導くアプローチも学びました。前回と比べ、見違えるほど積極的に留学生TAから何とか情報を聞き取ろうとする姿勢が目立ちました。
サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
2018/07/03 サイエンス英語I 英語イマージョン科学講座
テーマ 「たたら製鉄」
時間 6・7校時
場所 物理教室
対象 1学年理数科 40名
講師 北海道大学留学生 8名
ALT 1名
担当 理科教諭、英語教諭
内容 道内研修Aの事前研修を兼ねて、鉱石から金属を取り出す過程を、探究的に留学生TA、ALTと一緒にオールイングリッシュで学びました。科学英語は、英語で科学コミュニケーションを行うことができるようになることを目指して、4~5人グループに1人の留学生を配置して実施していますが、今年度は、科学的アプローチをデザインする力の育成も意識し、これまでの指導方法を改善・整理したオリジナルテキストを作成して実施しています。今日は1回目でしたが、「英語が嫌いなので気がのらなかったが、やってみるとすごく楽しかった」という感想にあるように、意欲的に取り組んでいました。今年度も下記のテーマの講座を実施する予定です。
「北海道の形成」、「札幌軟石の秘密を探る」、「恒星のスペクトル分析」、「鉱物に含まれる金属元素(JICA研修、オールセインツ高校生参加)」、「世界の異常気象~エルニーニョを探る~」、「自由落下運動の実験」、「エネルギー保存の実験」、「DNAの抽出実験」、「数学の四則計算」
特別科学講義A
2018/06/26 特別科学講義A
時間 6・7校時
場所 大ホール
対象 1学年理数科 40名
講師 北海道大学大学院工学研究院材料科学部門
マテリアル設計分野教授 三浦誠司 氏
担当 SSH推進部
内容 夏休みに実施する道内研修A(科学技術・ものづくりテーマ)の事前研修を兼ねた特別科学講義を実施しました。毎年恒例の講義となりましたが、今年度は、実物の金属標本を用いて金属の性質を学んだ後、結晶モデルを使いながら、金属の特性を探究しました。
SSH特別科学講演会
2018/06/12 SSH特別科学講演会
場所 第一体育館
対象 全校生徒、PTA希望者
講師 北海道大学農学研究院森林生態系管理学研究室学術研究員 森井悠太氏
(7月よりニュージーランド・マッセー大学客員研究員)
演題 「カタツムリをめぐる冒険」
担当 SSH推進部
内容 殻を振り回して天敵を撃退するカタツムリの研究で世界中に大きなインパクトを与えた、生態学の専門家で国際的に活躍する若き研究者、森井悠太先生をお招きして、生物の進化について、ご講演をいただきました。異なる資源への適応が表現型の分化を引き起こすという近年の進化生態学の通説に再考を迫る、天敵が生き物の多様化を促しているのではないかという研究、カタツムリを相棒に世界を駆け回る研究の醍醐味をお聞きすることができました。
U18 インターネット会議
2018/06/12 U18 インターネット会議
場所 物理教室
対象 2学年普通科 探究「Future Vision」
Sustainable Future Earth選択者23名
担当 理科教諭、英語教諭、ALT
講師 酪農学園大学准教授 吉中厚裕氏
内容 インターネット会議を活用して、オーストラリア・クイーンズランド州のマレーニー州立高校生との定期的な交流が始まりました。今年度は、「海洋プラスチック汚染と生物多様性の保全」をテーマに協働プロジェクトを行うことが、今回の会議で決まりました。月一回のペースでプロジェクトの計画、進捗状況、調査結果等を定期的に話し合います。英語で調査方法、進捗状況等を何度も聞き直したり言い直したりしながら伝え合い、英語でやり抜く力を育てます。
KSI家庭
2018/06/01 KSI家庭
場所 大ホール
対象 2学年理数科 40名
講師 札幌市厚別区保健福祉部健康・子ども課
子育て支援係1名
近隣に居住する協力親子5組、ボランティア2名
担当 家庭科教諭、実習助手、SSH推進部
内容 乳児とそのお母さん、お父さんに来校していただき、乳児との触れ合いを通して、子どもの今現在の関心事や成長の様子、親の喜びや思いなどについて質問し、答えてもらいました。自分の思いを言葉で伝えられない赤ちゃんの気持ちを表情や声など身体全部を使って伝えていること、男女が育児に関わることの大切さについて学びました。10月に再度来校していただけるのを、楽しみにしています。
KSI-III 課題研究マセマティクス
2018/05/09 KSI-III 課題研究マセマティクス
場所 講義室、数理教室他
対象 3学年理数科 40名
担当 数学科
内容 数学に関する専門性の高いテーマを設定してゼミ形式で行う課題研究が始まりました。6月末の発表会に向けて集中的に取り組んでいます。
探究「Future Vision」フィールドワーク
2018/05/02 探究「Future Vision」フィールドワーク
対象 2学年普通科全生徒
内容
16人のアドバイザーが取り組んでいる地域課題を理解し、社会との繋がりを考えるために、アドバイザーの活動場所等に出向きそれぞれのテーマについて学んできました。
今後、アドバイザー及び大学生TAと対話的に探究していきます。
訪問先
北海道大学(2グループ)、北星学園大学、北海道武蔵女子短期大学、円山動物園、NPO法人ezorock、かでる2・7、赤レンガテラス、札幌エルプラザ、もみじ台管理センター、北海道熱供給公社、サッポロファクトリー、まこまる、札幌市青少年科学館、北海道博物館、酪農学園大学
探究「Future Vision」テーマ選択
2018/04/20 探究「Future Vision」テーマ選択
対象 2学年普通科全生徒
内容
2年生の探究「Future Vision(FV)」がスタートしました。
今年度は、国連大学認定「RCE北海道道央圏」を推進している北海道大学の山中康裕教授をアドバイザーとして迎えプログラムを進めています。このFVは、大学、民間、NPO等で地域課題の解決に取り組んでいるアドバイザー及び大学生TAと一緒に、対話的に地域課題を探究する(社会との繋がりを考える)ことにより、地域課題を自分ごととし、新しいことに対応できる「学び方を学ぶ」、すなわち、協働性、創造性、批判的思考力等を効果的に育成するコンピテンシーベースの学びです。
今日は、テーマを選択するために、17名のアドバイザーをお招きし、取り組んでいる地域課題の説明を聞きました。
アドバイザー(所属)「テーマ」
山中康裕氏(北海道大学)「私たちは何を学ぶべきか?(2030年の学校教育を考えよう)」、萱野智篤氏(北星学園大学)「札幌をフェアトレードタウンに! 君たちは何ができるか?」、福原朗子氏(北海道科学大学)「香りの科学: え、そんなに大切なの?」、明田川知美氏(北海道武蔵女子短期大学)「“教育”って何だろう ~人が育つこと・育てること~」、佐竹輝洋氏(札幌市環境局)「持続可能で生活の質(QOL)の高い低炭素社会を築くために」、久保田学氏(北海道環境財団)「職業をとおして環境問題の解決にどのように貢献できるか」、清水誓幸氏(北海道中小企業家同友会)「中小企業の在り方、社会責任について、提言してみませんか?」、草野竹史氏(NPO法人ezorock)「野外ロックフェスのごみ問題はどうやって改善してきたか?」、立石喜裕氏(北海道NGOネットワーク協議会)「誰ひとり残さない社会を目指して」、阿部千里氏(アイヌ・先住民族電影社)「この大地でどう生きるか? 先住民族政策としてアイヌ政策を考える」、山岸奈津子氏(クライメイトPR)「自分の「好き」から世界を広げる、伝える、つなげること」、太田明子氏(太田明子ビジネス工房)「好きなことで働く?! 起業について考えよう」、松本公洋氏(NPO法人ゆうらん)「もみじ台団地から、ステキな未来のまちづくりを考えよう!」、田原沙弥香氏(NPO法人北海道グリーンファンド)「自分の電気を選ぶには?(エネルギーの選択について考えよう)」、大津大吾氏・佐藤弘人氏(サッポロ不動産開発(株))「サッポロファクトリーレンガ館の未来をデザインしよう!」、栗田敬子氏(特定非営利活動法人エコ・モビリティサッポロ)「高齢化時代のまちづくり モビリティとコミュニティを考える」、埀石寛史氏(札幌市青少年科学館)「子どもたちに、サイエンスのおもしろさを楽しく伝えよう」、水島未記氏・堀繁久氏・表渓太氏(北海道博物館)「野幌の自然を学ぶ・伝える 北海道博物館自然史エキスパートとともに」、吉中厚裕氏(酪農学園大学)「Sustainable Future Earth 持続可能な未来のためにできることは何?」